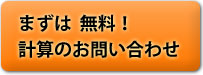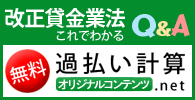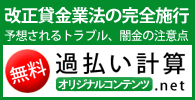- 改正貸金業法とはなんですか?
多重債務者の増加を背景に、問題の解決と利用者が安心して借入をできる仕組みを作るために改正された法律です。以下の規制が行われるようになります。
- 貸金業への参入条件を厳しくする
- 貸金業協会の自主規制を強化
- 夜間・日中の執拗な取り立て、契約時に死亡保険金で返済を締結などを禁止
- 貸付を行う際は、総借入残高が年収の3分の1を超えないようにすること
- 金融業者が貸付を行う際には、Dの条件を指定の機関に照会し、確認すること
- 金利の引き下げ
- ヤミ金融に対する罰則の強化
- 消費者の立場で関係のある部分は何ですか?
- 総量規制が実施されます
- 指定信用情報機関が設立され、年収や借入情報が収集されます
- 金利の引き下げ
- 総量規制とはなんですか?
借入金が1社で50万円を超える場合もしくは、複数の貸金業者からの借り入れが100万円を超える場合については源泉徴収票などの年収を証明する書類を提出必要があります。
※貸金業者は書類提出を求め、指定信用情報機関に報告する義務があります。
利用者は総額で、ここで確認された年収の3分の1までしか借りることができなります。
年収が300万円であれば、100万円までの借入となります。
- 本人の年収が無い場合(専業主婦(夫)などの場合)はどうなりますか?
一人での借入はできなくなります。
配偶者の同意書、及び、夫婦関係の確認ができる書類(住民票など)が必要になります。
また、借入できる金額は本人の場合と同様です。
- パートタイマー等での収入が有る場合はどうなりますか?
本人の年収の3分の1まで、もしくは、家計を共にする者との合算した所得の3分の1までの借入となります。また、合算する場合には家計を共にする者の同意書、及び、関係が確認できる書類が必要になります。
- 総量規制は全ての金融業者に適用さえるのですか?
- 消費者金融
- 事業者金融
- クレジットカード会社
- 信販会社
- クレジットカード会社が上がっていますがショッピング枠も計算されますか?
ショッピング枠は対象外となっております。
しかし、これに乗じてショッピング枠を現金化する業者も横行することが予想されます。
実際にはショッピングで利用した分がそのまま現金化されるわけではありません。
数%から10%くらいの手数料が取られます。結果として借金が増えてしまいますので慎重な判断が必要です。
- 指定信用情報機関とは何ですか?
各貸金業者が所属する、信用情報収集機関です。与信の流れは以下のようになります。
また、借入を行う場合には複数の信用情報機関に照会が行われます。
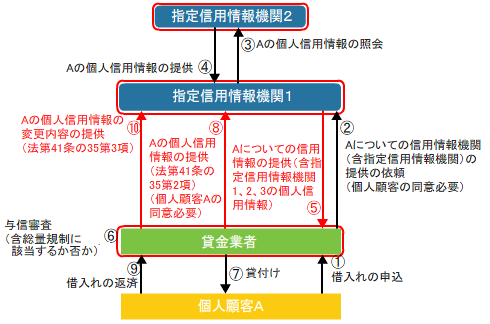
- 年収の3分の1を超える借入はどうしてもできませんか?
一部の除外、例外はあります。
【除外の事例】- 不動産購入のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額医療費の貸付け
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 手形(融資手形を除く)の割引
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(府令第10条の21第1項各号)
【例外の事例】
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け
- 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け
- 個人事業主に対する貸付け(府令第10条の23第1項各号)
- 既に年収の3分の1以上の借入があります。
この場合、新規の借入ができなくなります。
つまり、借入残高が年収の3分の1以下になるまで、返済しか行えない状態となってしまいます。
- 個人事業主の事業用資金も対象になりますか?
原則として総量規制の対象とはなりません。
しかし、貸金業者の資金繰りの悪化から、審査の厳しくなる業者も多くなりそうです。
- 借入は少ないですが、与信枠は50万円以上あります。
与信枠が50万円を超える場合も借入が50万円以上あるのと同様に、年収調査の対象になります。
- 金利の引き下げとは何ですか?
お金を貸す際の法律は
- 利息制限法(20%までの利息)
- 出資法(29.2%までの利息、2000年5月以前は40.004%)
また、20%以上29.2%の金利をグレーゾーン金利と呼び、過払いの再計算をする際の基本にしています。
- 過払い金の返還請求との関係は?
貸金業者として運営するための条件が、純資産2,000万円から5,000万円に引き上げとなります。
これによって中小零細の貸金業者は事業の継続が難しくなります。
また、今回の法改正及び、貸し倒れリスクの上昇から、貸し出しの審査基準を厳格化しており、新規申込者が実際に契約できる割合は大手でも4割程度にとどまっているようです。 貸付金額が少なくなるということは、企業として収益が少なくなるということです。
こういった様々な状況から、金融会社の経営状況が悪化し、過払い金が発生していても支払いができなくなるという可能性があります。
※倒産した場合債権は放棄されませんが、債務は放棄されるため
その他、ご不明な点ございましたらお問い合わせください。