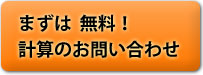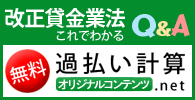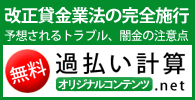法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的なサラ金や信販会社などのキャッシ
ングを利用している方のほとんどが利息を払い過ぎているのが実情です。
継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。
また、完済後でも10年間は返還請求が可能です。
【 利息制限法 】
利息についての基本的な法律。金銭消費貸借上の契約及び損害賠償の予定額について、利息の観点から制限を加えた法律。
| 元本10万円未満 | 利息 | 年20% |
| 損害金 | 年29.2% (平成12年5月31日までは年40パーセント) |
|
|
元本10万円以上〜 100万円未満 |
利息 | 年18% |
| 損害金 | 年26.28% (平成12年5月31日までは年36パーセント) |
|
| 元本100万円以上 | 利息 | 年15% |
| 損害金 | 年21.9% (平成12年5月31日までは年30パーセント) |
サラ金や信販会社などが、上記制限を越えた利息で貸付をしているのは、
利息制限法とは別の出資法に定める利率(上限29.2%)を基準としたもの
(但し、平成12年5月31日までは40.004%)を上限として有効な利息として受領してもよいと規定されているからである。
> 出資法とグレーゾーン金利の詳細はこちら
みなし弁済とは、貸金業の規定等に関する法律(以下「貸金業法」という。)43条1項、3項により
有効な利息又は賠償の支払いとみなされる弁済をいう。
貸金業者は、貸付にかかる契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で
定めるところにより、所定の事項についてその契約内容を明らかにする書面
(実務上「17条書面」呼ばれる。)を相手に交付しなければならない。(同法17条1項)
また、貸金業者は、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、所定の事項を記載した書面
(実務上「18条書面」と呼ばれる。)を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)。
これらの規定は貸金業者が契約内容を説明した書面や弁済の受領証書を借主に交付しないために
契約の内容や弁済の有無をめぐって紛争が頻発したことから、こうした紛争を予防する目的で
置かれたものである。そして、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(みなし利息を含む)の契約又は賠償額の予定に基づき、債務者が利息又は賠償として任意に
支払った金銭の額が利息制限法1項1条、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、その支払いは有効な利息又は
賠償の支払いとみなされるのである。
もっとも、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強く、
裁判実務上は、みなし弁済の成立が認められる例はさほど多くはない。
裁判例においてしばしば問題となる論点は次のとおりである。
| 1. | 17条書面及び18条書面の交付があったか。 |
| 2. | 交付された書面が17条書面及び18条書面としての要件を満たしているか。 |
| 3. | 18条書面の交付が弁済「の都度、直ちに」なされているか |
| 4. | 借主のした弁済が「任意に」支払ったものといえるか。 |
| 5. | 借主のした弁済が「利息又は賠償として」支払ったものといえるか。 |
| 6. | みなし弁済が成立しない場合において、超過支払部分の不当利得返還義務を負う資金業者悪意の受益者(民法704条)といえるか。 |
※ フリー百科事典『ウィキペディア(wikipedia)』参照